家庭教師ブログ
家庭教師ブログ
2025.06.27
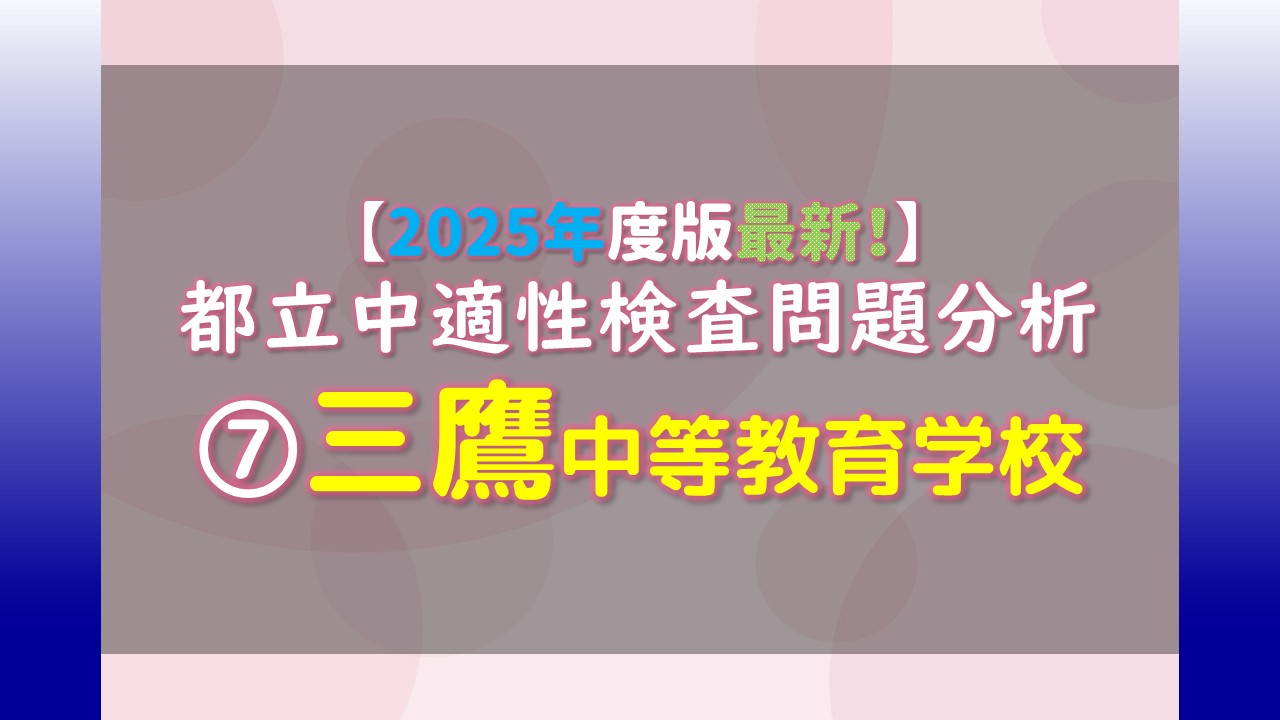
お子様の成績など詳細を伺い、マンツーマンカリキュラムで
三鷹中の対策授業を行っております。
三鷹中対策コースのご案内はこちら☟
【PR】
☆小学生の都立中受検対策に☆
家庭教師をお探しなら
~マンツーマン授業をご家庭で!~
派遣型家庭教師Campのご案内はこちら☟
こんにちは。家庭教師Camp事務局です。
本日のブログは、
2025年度版最新!
都立中適性検査問題分析 ⑦三鷹中等教育学校 です。
都立三鷹中、都立中を志望している方、必読です!
〈文章・出典〉
文章1:佐藤いつ子「透明なルール」による
文章2:落合由佳「要の台所」による
〈出題形式〉
昨年度に引き続き2つの物語文からの出題でした。〔問題1〕〔問題2〕の読解問題の難度は昨年度よりやや易化しました。〔問題3〕の作文に関して、テーマとしては書きやすさがあるものの「問われ方」が例年と多少違うため、戸惑った受検生もいるかもしれませんが、難度は平年並みだったと言えます。
〔問題1〕本文表現の内容を問う問題(20字以上30字以内)
「透明なルール」について本文での二つの考え方を説明する問題でした。本文では、「同町圧力とかの目に見えないルール」、「とかの」とあるので、具体と抽象のイコール関係が成り立ちます。また、「透明なルールって同調圧力だけじゃない」と発言し、数学オリンピックのエピソード(具体)について述べています。その直後に「自分が自分に作ってしまう、透明なルール」と具体内容を抽象化しています。
「透明なルール」=「同調圧力」「自分が自分に作ってしまうもの」と読み取れます。「考えていたり、思ったりしているのに意見を言わない」「みんなの反応を勝手に決めつけて自分で自分を縛っていた」という内容があるのでこれらをヒントにして解答をまとめます。平易な問題であり、必答問題だったと言えます。
〔問題2〕本文表現の内容を問う問題
「人と人とのあいだのことも同じだよ。」という発言から話者がどのようなことを伝えようとしているかを答える問題でした。「も」に注目すると「料理」と同じであることが読み取れます。直前に「どうせまずくなる』なんて思いながら料理はしない」、直後に「相手と一つの料理を~」とありますが、こちらは「料理の話」、つまり「人問関係」を例えている内容です。問は「人問関係」に関してなので「これらの話」を人問関係に当てはめている「お互いに力を合わせる」という箇所を中心に考えていきます。
「1つの料理を作るようなもの」とあるのでこれと同じように、人問関係も「自分だけがんばる、相手に任せるのではなくお互いに力を合わせる」という要素が解答に使用できます。また、悪い方ばかり捉えてはいけないという要素も解答を作成するヒントとなりました。〔問題1〕より難度は高く、適性検査Iの点数を左右した一問です。
(問題2)指定部分の理由を答える問題
そろりさんがなぜメニューに「自信が持てるあんバタートースト」という名前を付けたのかを答える問題です。設問にある「( )というメッセージをお客さんに伝えるため。」という部分は解答のヒントに使用できます。さらに設問には「そろりさんの意図を想像して」という内容がありますので、文章中でのそろりさんの発言以外にも広く注意をして、考えていく必要があります。この小説文で中心になっている「自信が持てるあんバタートースト」、そこから「そろりさん」が伝えるメッセージを読み取るという点でこの小説文の主題を読み取らなければならない問題です。主題の読み取り、さらに〔問題1〕も〔問題2〕も広く文章をみる必要があり、前年度と比べ難化しています。文章中の「だから自信を持つことが大切なんですよ」など、そろりさんが発言した部分から考え、意図を想像して解答を作る必要があります。この問題の正否は適性検査Ⅰの点数に大きな影響を与えることになります。また60字以上70字以内の記述ですので、記述の型を意識して解答を作ることも大切でした。
〔問題3〕作文問題(360以上400字以内)
近年は段落を設けず1ますめから書き出すというものでしたが、今年度は段落を設けて1ますめを空けるという指示になりました。そのため、〈きまり〉を注意深く読む必要がありました。また、近年にはなかった段落での内容指定がありました。第一段落では 81字以上100字以内で自身の意見を考き、第二段落でその理由を書くというものます。意見に関して細かい文字数指定があるので、内容をまとめる力、学数に合わせて表現する力が試されました。理由に関しては自身の意見の根拠としての妥当性があるのか、論理的に説明ができているのかが問われています。作文のテーマにしては取り組みやすいものだったので、「書かなければならない内容」を条件にしたがって書けているかどうかが重要でした。
〔文章1〕の「透明なルール」に縛られて、自分の意見を表明しない様は、〔文章2〕でいう「相手と一つの料理を作る」状態にならずに、どちらか一方だけが作っている状態となります。そのため、「お互いに」「協調」「共同」などが重要な要素でした。自分の考えを相手に伝える、また相手の意見も尊重して協力していくという方向性の内容が考えられます。「自分でマイナスな方向に決めつけない」という内容も、両者に共通する要素として挙げられます。例年の三鷹中の適性検査Ⅰというよりも、共同作成問題の作文問題に近く、他校も含めて様々な問題に取り組んでいた受検生には解きやすい問題でした。
1⃣は三鷹中の独自作成問題で、算数分野からの出題でした。2⃣・3⃣は共同作成問題です。
1⃣算数の力を総合的にみる問題
三鷹中の独自作成問題で、算数分野からの出題でした。今年度はスーパーマーケットでの買い物を題材として、与えられた条件に従って試行や計算を行う問題が出題されました。昨年度は小問3問の構成でしたが、今年度は小問2問の構成で、1問に対する作業量が増えています。なお、〔問題2〕の記述量が多いため、説明として書くべき文章量はそこまで減っていません。また例年の傾向と異なり、今年度は円に関する問題が出題されませんでした。自分の意見を書く問題も出題されておらず、出題形式が他の都立中適性検査の算数の問題に近づきました。全体的に、難度は例年並みだったと言えます。
〔問題1〕組み合わせの場合の数を考える問題
バーコードについての条件を読み取り、数字を表す配線の組み合わせが何通りあるかを答える問題でした。合計が7になる4つの軽数の組み合わせをすべて見つけなくてはならず、場合分けしながら正確に数え上げていく力が求められます。また、数字の組み合わせを考えた後に、白と黒を反転させたパターンを考えるため、数え上げた場合の数を2倍するのもポイントとなりました。令和4年度でも類似の組み合わせの問題が出題されており、今回同様に、数え上げた場合の数の数を2倍する必要がありました。令和4年度の問題よりも組み合わせのパターンが多く、時問がかかるようになっていますが、考え方と要点は近いです。そのため過去問演習の際に、求め方にもこだわっていた受検生にとっては、非常に解きやすい問題だったと言えます。合否を分ける可能性のある、重要な一問でした。
〔問題2〕直方体の詰め方を考える問題
(1)は、ある容器にお菓子の箱AとBを複数個、隙問なく詰めるときの個数と入れ方を説明する問題、(2)は、その入れ方でお菓子の合計金額が最も高くなることを説明する問題でした。与えられた条件は少ないものの、答えるべきことが複数あるため、解法や記述の方針を素早く立てる必要がありました。「容器に隙問なく詰めること」から、箱それぞれの辺の長さをもとに入れ方の見当をつけるとよいでしょう。これを手掛かりに、容器の内のりと箱の辺の長さを利用して図を描きながら整理していくと、映問のない箱の入れ方を見つけることができます。合計金額が最大になる理由については、まずどちらの箱が値段の割に体積を取らないのかを考えたうえで、なるべく体積あたりの金額が安い方の箱で容器を埋め、次に残った隙問の使い方を比較する必要があります。何パターンかの試行を要することや、何から手を付けるのかを自分で判断しなければならないことも含めて、近年の三鷹中としてはやや珍しいタイプの問題だったと言えます。難度が高いため加点できた受検生は少なく、あまり差のつかない問題だったと言えます。
2⃣製品のリユースやリサイクルについて考える問題(共同作成)
令和3年度から引き続き小問2問の構成ですが、〔問題1]は、(1)と(2)に分かれており、(1)では割合の計算が出題されました。
共同作成問題の適性検査日大問2で割合の計算が出題されたのは、平成30年度以来です。大問全体の話題はリュースやリサイクルといった循環型社会に関するもので、受検生にとっては見慣れたテーマでしょう。また、会話文や資料は標準的で取り組みやすい内容であったため、2問とも正解するべき問といえます。解答に必要な要素を会話文や資料から適切に読み取ったうえで、問われていることに対しての答えをわかりやすく表現することが大切でした。
〔問題1〕割合を計算し、資料を比較して分析する問題
(1)は、図2または図3から選択した資料における循環利用率を計算したうえで、その結果が衣服の循環利用率と比較してどちらが高いかを答える問題でした。計算自体はどちらを選択しても3桁÷3桁と平易な割合の計算なので、確実に正解したい1問と言えます。ただし、ここでの選択は(2)にも関わるため、ただここを速く確実に解くだけでなく、そちらも見据えての選択をしておきたい1問でした。
(2)は、製品ごとの循環利用における特徴を比較し、共通点と異なる点を説明する問題でした。ひとつの問題で解答すべき内容が複数ある形式は、5年連続の出題となりました。問題の条件から、「ペットボトルと~の循環利用の共通点は~であり、異なる点は~である。」といった解答の枠を作り、必要な情報を読み取って完成させると解きやすいでしょう。共通点はペットボトル(図2)を選んでも、紙(図3)を選んでも自明ですが、異なる点は紙の方が答えやすかったため、(1)を解く時点で、こちらまで目を配っておく視野の広さがある受検生は、多少なりここで時問を節約できたでしょう。
〔問題2〕複数の資料を組み合わせて説明する問題
衣服の循環利用率を高める取り組みによって、消費者の意識や行動がどのように変化して循環利用率が高まるのかを説明する問題でした。[問題1](2)と同様に、解答に用いる資料を受検生に選択させる形式は6年連統の出題となりました。この問題を正解する一番のポイントは、花子さんの「循環利用率を高める意識や行動もあれば、そうでないものもあります。」というセリフです。この観点で図4、図5、図6を見ると、無計画な服の購入、まだ着られる衣服を可燃ごみとして捨ててしまう、などが「そうでない」意識や行動であることが分かります。そして、その上でカードを見ると、そういった問題点を改善し、図4、図5、図6の「循環利用率を高める意識や行動」に当たるものへ導いていることが分かります。例年通りの都立中適性検査文系の、セオリー通りの解法が身についているか否かで正否が分かれる一問でした。
3⃣シャボン玉の性質について考える問題(共同作成問題)
近年の傾向通りの問題でしたが、例年よりも会話文が少なくなり、実験の手順の説明が詳細化されました。問題文中の表現も含めると、これまでであれば実験結果の着眼点を示唆するだけであったものが、それに加えて検証の仕方まで示唆されるものとなっており、大幅に解きやすくなったと言えます。しかし、思い込みなしに丁寧に問題文を読み取らないと、読み取り方が問違いやすい箇所があり、落ち着いて処理できたかどうかが重要でした。共同作成の適性検査山は、算数系の大問1の方が難度の高い年度と、理科系の大問3の方が難度の高い年度があります。今年度は解答の記述量の面で、大問3の方が難度が高かったと言えるでしょう。適性検査全体の難度が例年よりも易化したことと合わせて考えると、学校によっては合否の決め手となる大問と言えます。なお、シャボン玉とその体積、割れ方などを題材とした問題は後期日曜特訓第14回の適性検査I大問3と同一でした。このため、enaの後期日曜特訓を受講している多くの受検生は、大変取り組みやすい問題だったと言えます。
〔問題1〕シャポン玉の割れやすさに関する問題
シャポン玉は砂糖水から作ると割れにくい、ということについて、望ましい濃度を探る実験についての問題でした。食器用洗前、濃度、などのキーワードは、令和4年度の問題を考様させます。あくまで題材の近さであり、問われているものは異なりますが、問われているものを正しく読み取ると、実は令和6年度の(問題1)ととても似ています。条件を1つ変化させた実験2つの結果をふまえて答えを出す、結果をただまとめるだけでなく、その内容を換言する一手問がある、という特徴が踏題されています。そのため、近年の過去開をしっかり解きこんでいった受検生にとっては解きやすい一問でしたが、完全に正解した受検生はそこまで多くないと思われます。鍵となるのは前述の「換言」で、問われているのはシャポン玉の「体様」の比較ですが、資料には体積ではなく、空気入れを押した回数がまとめられています。「回数が多い→シャボン玉に入れられた空気が多い→体積が大きい」という置き換えを正しく説明しきれているかどうかが記述のポイントになります。こういった問題で点数を取り切れるように、過去問の演習をする際には、ただその問題を例題として扱うのではなく、肝となる部分はどこか、を意識して行うとよいでしょう。
〔問題2〕シャボン玉の時問経過による割れ方に関する問題
時問経過により、シャボン玉のまくをつくる液が徐々に下部にたまっていき、薄くなった上部から割れていくことについての実験結果の考察を答える問題です。実験の手順と結果は大変分かりやすく示されており、結果に対しての考察の検証をする実験まで行っていますから、現象についての理解は平易でした。そのため、この問題における得点の差は、問題文の条件通りに解答を作ることができているかどうかによるものが大きいでしょう。適性検査の問題文としての正しい読み取り方をすると、解答には4つの要素を入れなければなりません。それを正しい言語表現でまとめられたかどうかが重要でした。特に、前述の日曜特訓の問題で、現象(時問経過により、シャボン玉の液が下へいくことで、上部がうすくなり割れる)について問うほぼ同一のものを経験していますから、enaで日曜特訓を受講している受検生には特に解きやすい一問であったと言えます。
苦手な単元は今から対策して基礎固め~応用問題を読み解く力をつけましょう。
マンツーマン指導の家庭教師Campでは、
勉 強 に ま つ わ る あ ら ゆ る お 悩 み に お 答 え し ま す!
苦手科目・単元の克服や、
応用問題でどうしてもつまづいてしまう
あと◎◎点伸ばしたい
……というお悩みまで、
勉強のプロに聞いてみよう!
東大はじめ難関大学出身の教師に教わってみませんか?
25分からOK・オンラインでご都合のよい時間の授業OK
まずは体験授業から!
お子様の成績など詳細を伺い、マンツーマンカリキュラムで
三鷹中の対策授業を行っております。
三鷹中対策コースのご案内はこちら☟
【PR】
☆小学生の都立中受検対策に☆
家庭教師をお探しなら
~マンツーマン授業をご家庭で!~
派遣型家庭教師Campのご案内はこちら☟
難関中高大受験のための
オンラインマンツーマン指導
月額 6,380円(税込)~
入会金・管理費・解約金はありません